INFORMATIONお知らせ
【中国自動車最新事情】合弁メーカーに求められる「合弁2.0時代」。トヨタとホンダの新型EV戦略2025.03.20

3月7日、東風ホンダは新ブランド「燁」の第一弾として「東風ホンダ S7」を発表した。シングルモーター仕様「開拓者版」は25.99万元、デュアルモーター仕様「領航者版」は30.99万元という価格設定だ。その前日、広汽トヨタは「鉑智(ボージ、bZ)3X」を発表し、価格は10.98万~15.98万元。特に14.98万元の「520 Pro智駕版」はOrin-XチップとLiDARを搭載し、高速道路および市街地でのナビ付き運転支援や自動駐車機能を備えている。
対照的に、S7はより高価格でありながら、高速道路での運転支援機能のみにとどまり、宣伝の重点は「バッテリー技術」と「安全性能」だ。高強度鋼の使用比率が68%に達し、バッテリー容量は89.8kWhを誇る。一方、鉑智3Xはコストの低いリン酸鉄リチウム電池(50.03~67.92kWh)を採用。サイズも異なり、鉑智3Xは全長4600㎜、横幅1850㎜、高さ1660㎜、ホイールベース2765㎜。S7は全長4750㎜、横幅1930㎜、1625㎜、ホイールベース2930㎜と一回り大きい。
それでもこの2台が比較されるのは、発表時期が近いこと、トヨタとホンダが市場で常に比較対象とされること、そして両者の中国市場戦略の方向性を象徴するモデルだからである。
情報源
新车卖 10.98 万元的丰田想通了,但新车卖 25.99 万的本田还没有
「現実的な選択」がもたらしたトヨタの大量受注



広州モーターショーで鉑智3Xを出展していた
一部メディアによると、同車は広汽埃安(GAC Aion)の第2世代「Aion V」、通称Aionティラノサウルスをベースに開発されたという。同車は広汽埃安がブランド再編後に投入した重要モデルで、価格は12.98万元から。レーザーレーダーを搭載した運転支援モデルは16.98万元から販売されている。サイズやホイールベースは同車よりもやや大きく、運転支援センサーの構成も若干異なる。
しかし、鉑智3Xは単なる車名変更のみの同型車(バッジエンジニアリング)ではなく、Aion Vをベースに独自開発が施されたモデルだ。この関係は、「トヨタ・レビン(雷凌)」と「トヨタ・カローラ」のような双子車とは異なり、両者を直接結びつける人が少ない要因となっている。
合弁ブランドEVの苦戦とその理由
これまで合弁ブランドのEVは中国市場で苦戦を強いられてきた。その主な理由は以下の2つ。
①供給チェーンの閉鎖性
②製品開発が現地ニーズに合致していないこと
例えば、前モデルのトヨタ「bZ3X」は、ユーザーの実用性を無視した設計の典型例だった。中国ではbZ3Xを「認証コード」や「値下がり三倍速」と揶揄する声も多く、大幅値引きの末、ライドシェア市場へと流れる結果となった。
しかし、鉑智3Xでは広汽トヨタがローカルサプライヤーを積極採用。EV分野ではローカルサプライヤーのほうが技術力とコスト面で優位であり、電動モーター、バッテリー、レーザーレーダー、運転支援技術の多くを中国メーカーから調達。その結果、ローカルサプライヤーの比率は65%に達し、トヨタの中国市場におけるサプライチェーンのローカライズ比率としては過去最高を記録した。
「トヨタらしさ」と品質基準の維持
また、発表会や提供された資料からも、広汽トヨタの態度は非常に謙虚だ。
このコメントからも、広汽トヨタが中国市場の変化を受け入れ、積極的に適応しようとしている姿勢が見て取れる。
「合弁2.0時代」とは何か
しかし、「合弁2.0時代」では、製品の企画・設計・開発の主導権が中国市場に近づいた。これにより、広汽トヨタは「鉑智3X」のようなローカライズが進んだEVを投入することになった。
鉑智3Xはワイヤレス充電機能が50Wに対応し、冷却ファンまで搭載している。この仕様は中国の新興EVメーカーでは標準化しつつあるが、海外メーカーでは依然として珍しい。
また、同車はほぼ同等のスペックを持つ「Aion V」よりも安価に設定されている。これは、広汽トヨタが「合弁ブランドのプレミアム価格」や「広東省のトヨタ信仰(老広信仰)」といった過去の概念を捨て、「現実的な製品と価格が最も重要」という結論に至ったことを示している。
今回の大量受注は、トヨタが「合弁2.0時代」において適応を進め、競争力を取り戻すきっかけとなるかもしれない。
東風ホンダ S7は普通でありながら自信満々、それは成功体験の諦めの兆しか

例えば、bZ3Xは実用性を重視し、エントリーモデル(12.98万元)でも50Wのワイヤレス充電を搭載している。一方、S7はそれよりはるかに高価なモデル(開拓版、約26万元)でも20Wのワイヤレス充電しか備えていない。
さらに、インテリアのディスプレイもトレンドに適応できていない。10万元台の新興EVですら「大型ディスプレイ+スマートコクピット」が標準になりつつあるなか、S7は12.8インチ+10.25インチの「小型デュアルスクリーン」を採用している。
東風日産はすでに方向転換

東風日産のN7
機能は高いけど、それだけでは足りない
もちろん、S7は基本的な安全性能はしっかりしている。例えば、5層構造のAピラー、1.2万トンの一体成型バッテリーシェル、50:50の重量配分など、基本スペックに大きな問題はない。しかし、中国の消費者は、単に「無難なクルマ」を求めているのではなく、価格に見合う「ワクワクする要素」も求めている。
30万元クラスのEV市場には優れた選択肢が多数存在する。S7がこの価格帯で「発光エンブレム」「リアバッジ」「格納式ドアハンドル」を売りにしているのは、市場環境を理解していない証拠だろう。
合弁ブランドはどう生き残るのか?


長安マツダのEZ-6は長安汽車ブランド深藍SL03のプラットフォームを採用
一方、東風日産の「N7」は、東風奕派(eπ)007をベースに開発され、車体サイズを拡大しつつADASも強化されている。同じ合弁ブランドでも、日産は適応を進めている。また、長安マツダの「EZ-6」も深藍SL03のプラットフォームを活用し、EV版は補助金適用後9.98万元からという戦略的な価格設定を実現している。
結論として、合弁ブランドは「ブランドプレミアム」や「過去の栄光」にすがるのではなく、中国市場に適応し、スマート化を進めることが求められている。
現在、広汽トヨタは完全にこの流れを理解し、東風日産もその方向へ進みつつある。しかし、東風ホンダはまだその転換ができていないようだ。
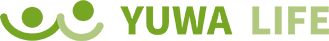

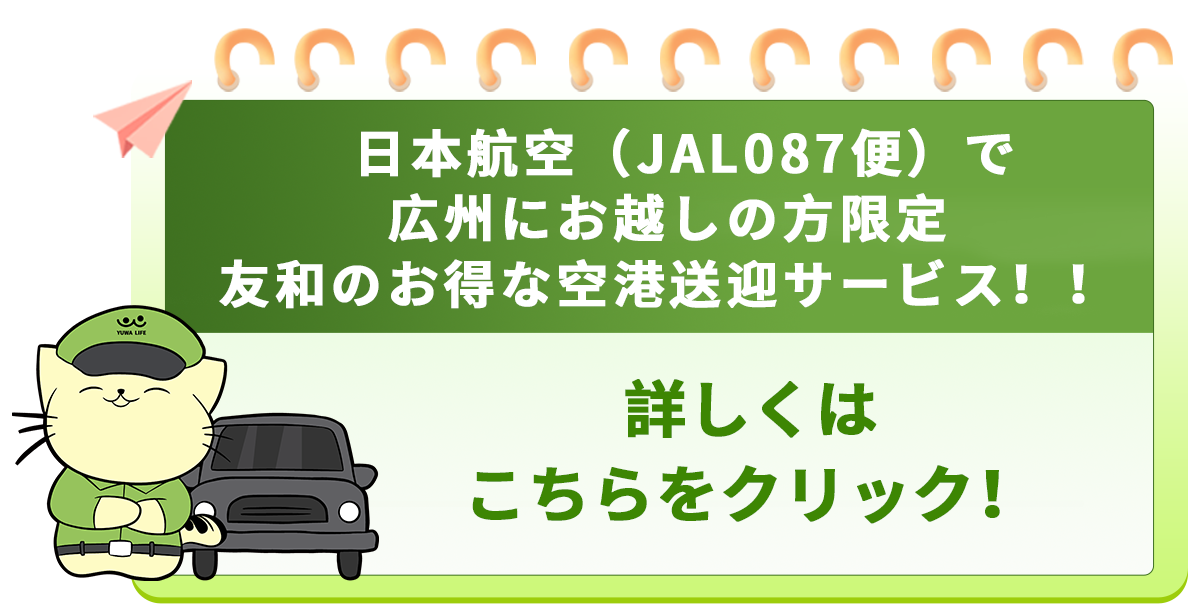









 企業公式アカウント
企業公式アカウント 担当者直結WeChat
担当者直結WeChat 友和チャンネル(YouTube)
友和チャンネル(YouTube)